こんにちは!ダイバーラウンジです。
先日、長野県北アルプスの槍ヶ岳で相次いだ地震の影響で落石が発生し、一部の登山者が動けなくなってしまったことがニュースになってましたね。
登山を何回かかじったことある僕からしても「もし自分が登ってる最中に地震に出くわしたら・・・」と思うとゾッとするニュースでもありました。
と同時に、そう言えば、ダイビング中に地震に遭ったらどう行動すべきなんだろう?ということが気になりました。
ざっくり調べてみたら色んな海の事例やノウハウが出てきたので、自分へのメモも兼ねて、記事として情報をまとめていこうと思います。
※今回は個人的に集めたに過ぎない情報が多いかもしれません。役に立たない情報を載せたいわけではないので、もし間違いなどありましたらご指摘いただけると嬉しいです。
ダイビング中の地震は気付けるのか?
地震が起きたらどう行動するか、の以前に、そもそもダイビング中に地震が来たら気付くか?という点についてです。

とりあえず、港やビーチ際に関しては陸上にいるのと変わらないレベルで気付きそうですよね。このパターンはあまり特殊に考える必要はなさそうです。

ボートに関しては、恐らく水深によります。ある程度水深のある場所では気付かないパターンもあるようですが、港や桟橋に着港していた船が尋常じゃない揺れを観測していることが、近畿運輸局がまとめている「津波に遭遇した船の行動事例集」でも確認出来ます。
平成23年3 月11 日14 時46 分、大船渡 港野島桟橋Bバースに於いて今まで経験した事 の無い揺れと突き上げる様な衝撃に直面し、直 ぐさま自室の窓から桟橋と本船の舷側を見る。 桟橋は上下左右に大きく揺れ、ベルトコンベア 上のセメントが白煙を吹き上げていた。
そして、問題は水中ですね。まさに潜ってる真っ最中に地震が来たとして、それに気付けるかどうか。
オーシャナさんの過去の記事やOFFICE TAKUZOさんの記事、実際に地震が発生した時の海中を記録した映像などを漁ってみました。
動画、結構上がってるものですね。個人的には2つ目の体験談の動画(というかテレビの特集番組?)が観ていてまぁまぁ怖かったです。
こんな感じで色々漁ってると、いくつか共通して言及されている兆候があるなと思いました。
- 音:
「ドン」という爆発音や破裂音、または「ゴゴゴ」という地響きともボートエンジンともとれるような音がする - 水中の生き物:
突然視界やダイビングポイントから消え失せるなど、普段とは異なる行動をとる - 水底の状況①:
岩礁やサンゴ、海藻などが激しく揺れ動く。場合によったら海中を飛び回るような感じになる - 水底の状況②:
海底の砂などが煙のように巻き上げられ、「え、透明度30cm?」レベルで視界を覆う
この辺りが「地震かもしれない」と疑って良いかもしれない兆候になるようです。
音や生き物の様子からそれを判断するのは難しそうですが、後半2つの現象がハッキリ出てきたら、気付ける可能性は高いかもしれないですね。出くわしてみないと分からない点でもありますが・・・
地震が来たらどう行動すべきか
では、実際にダイビング中に地震が来たら、特に最大のポイントである津波の被害を避けるためにどう行動すべきなんでしょうか?
3.11の際は、地震が発生して大体30分ほどで津波が来ていると観測されておりました(参照はこちら)。この30分の間にどこまで行動できるかが鍵になるわけです。
色々と調べてみましたが、日本でダイビングをする上で地震が来た時の共通のガイドラインは無いように思えました(探せてないだけかもしれないです、あったらご指摘ください!)。
ただ共通のガイドラインが無いだけで幾つか独自に決め事を行ってるダイビングショップさんも多かったので、それらの情報をもとに、それぞれのパターンを考えておこうと思います。
港やビーチ際にいる場合

ビーチダイビングにしろボートダイビングにしろ、ダイビングが始まる前、または終わった直後に港やビーチ側にいる場合です。
これはもう、やることは1つですね。高台に逃げましょう。
当然ですが、津波が真っ先に到達する港やビーチ際は最も危険な場所となるわけで、津波の影響をモロに受ける高さでもあります。何よりもまずそこから離れましょう。
器材や荷物?こればかりは捨て置きましょう。防災用の荷物がその場にあるなら別ですが、そうでない場合は可能な限り手荷物を少なくし、余計な体力を削らないようにして行動するのがベストっぽいです。
ボートにいる場合

ボートダイビングをしに船で沖合に出てて、潜水中ではなく、ダイビング前だったり休憩中な場合です。
この時とる避難行動は、他の船や漁船がとるべき行動とそこまで変わらないはずです。
水産庁がまとめてる「災害に強い漁業地域づくりガイドライン」や、総務省の東海通信局が作成している「漁業用海岸局及び漁船の津波災害対策ハンドブック」によれば、地震発生直後に沖合に出ている船の避難行動は基本的に
直ちに、水深50m以深の海域に出ること
とされています。この海域は「一時避難海域」と呼ばれ、この避難行動は「沖出し」と呼ばれています。
ボートに乗ってる時に地震が発生したら、津波の影響を受けにくい沖合に避難した方が良い、というわけですね。
その後に更に沖合に出る必要があるのか、どのタイミングで帰港できるかは、実際に津波警報など情報を通信で取りつつ判断するしかありません。つまりこればかりは船長に判断を委ねるしかないのですが、とりあえず「地震が来たらボートが更に沖に出たら、それは正当な避難行動だ」と踏まえておくだけでも違うと思います。無闇に「すぐ港帰るべきじゃないか」と慌てる必要もなくなります。
水中にいる場合

では一番の問題である、ダイビング真っ最中に地震が来たらどう行動すべきか。
前述した兆候から地震だっと気付けたら、その後どう行動したら良いのか、せめて指針を知りたいところです。
緊急浮上が可能な場合
ダイビングが始まった直後だったり、終わる直前だったり、水深がそこまで深くなく緊急浮上が可能な場合であれば(間違っても急浮上はしないように気を付けた上で)浮上してビーチ・ボートに戻り、前述の「港・ビーチにいる場合」と「ボートにいる場合」それぞれの避難行動を取った方が良さそうですね。
はじめからそこにいる場合と比べたら少し時間の勝負となり急ぐ必要がありそうですが、特にビーチダイビングであれば陸に近い分、兆候に気づきやすいかもしれません。
十分な水深があれば影響は少ない、と言うけれど・・・?
前述の行動は、安全性を確保した上でビーチ・ボートに比較的早く到達できる場合のパターンです。
これが水深が深い場所にいて緊急浮上するには危険過ぎたり、既に引き波などが始まって流れが激しくなっている場合ではまた異なってきます。ボートの動きは激しくなって近付けないでしょうし、ビーチには引き波で辿り着けない可能性も高い。
色々記事を見ていると
十分な水深があれば津波の影響は少ないからむしろ動かないほうが良い
という説を見かけます。津波で多少の流れの影響は受けつつも、浅瀬で津波をモロに喰らうより危険は少ない、という訳ですね。
確かに慌てて浮上したりエキジットしようとするより、事が起こってしまってるなら動きの激しい水面にいるより水中にいた方がよりダメージは少なそうです。
たださっきの3つ目の動画みたいに「水中が洗濯機みたいになって水深17mから5秒で2mくらいまで打ち上げられて、また下がってった」みたいな状況が視界悪い中で起こると思うと、だいぶ怖いっちゃ怖い・・・状況把握していかにパニックにならないかが大事そうです。
場合によっては船と同様の避難行動を
さっき「十分な水深があれば津波の影響は少ない」と書きましたが、これは前述した船がやる「水深50m以深の海域に出る」という避難行動と同じ理屈になります。
てことは、ダイバーとしてもこれと似たような避難行動を取るのは理にかなう、ってことになります。つまり、
- 浮遊物の衝突、波の上下動の心配が少ない沖合の方まで泳ぐ(なるべく水面に出ない)
- ある程度泳いだら浮上し、BCの浮力を保ち、周囲に気を付けながら浮かんでる
- 同様の避難行動を取っている船などの助けを待つ
船に助けを求めないといけない、というリスクはありますが、海の動きが既に激しくてビーチやボートに戻れなさそうであれば、このような避難行動を取ることも1つの選択肢と言えそうです(これをTwitterで言及してくださったMarine Sweeperさん、ありがとうございます!)
※ここまで書いた情報は、以下の記事等を参考にまとめました。各記事により詳しい情報なども記載されているので、良かったら見てみてください。
- ダイビング中に地震が起きたら?東日本大震災時、水中にいた作業ダイバーの証言
- 緊急事避難路について(伊豆ダイビング 田子シーランド)
- ダイバーなら知っておくべき水中で津波に遭遇したダイバーたち11人の壮絶な体験記録
- 【緊急掲載】もしダイビング中に地震に遭遇してしまったら
終わりに
色々と書きましたが、どこでどういう避難行動を取るべきかは、地域や、それぞれのダイビングポイントによっても変わってくると思います。どんな状況でも臨機応変に動けるよう、ここまで書いた情報はあくまで頭の片隅に置いとく安定剤的な役割になってくれると嬉しいです。
最後に、ちょっと違う角度の話を。
この記事を書いてる僕は今、神奈川の地元葉山の海沿い、それも漁港のすぐ真ん前に住んでおります。当然、津波が来たら真っ先にやられる場所なので、もし大きな地震が来たら、同じく葉山の山沿いにある実家に逃げる、と基本的には決めています。
で、その話をする際こんな会話を父としました。
僕「向かい側にでかい老人ホームがあるじゃん。避難絶対大変だよね。いざとなったら手助けしたいんだけど、どこまで手伝えるもんなんだろう」
父「余計な手出しはしない。共倒れになる可能性が高いから。まずは自分の安全を確保することを最優先すること。人を助けるのはその後」
そういうものなのか!?とその場では思ってしまいましたが、後日とあるテレビ番組でお笑い芸人のサンドウィチマンが、宮城の学校に訪れた際に(多少文脈は違うものの)全く同じことを子ども達に話しており、なるほどなと思いました。
これは「人助けをするべきじゃない」って言う話ではなく、物事の優先順位をどう立てるか、という話です。まずは、自分が助かること。緊急事態においては、それを一番に考えなければいけない、ということですよね。これは決して独りよがりではなく、重要な順序立てだと思います。
もちろん、団体行動をしないとスムーズに動けない場面もあるし、我先に過ぎて人を陥れるようなこともNG。ただ、自分の命や安全は、何より自分で守らなければならない。それが出来て初めて、万全に人を助けられるようになる。
当たり前のようでいて、いざとなったらきつい判断をする必要もあるかもしれない話なので、時々振り返って考えてみようと思っています。
てなわけで今回は以上になります!
お読みいただき、ありがとうございました(^^)






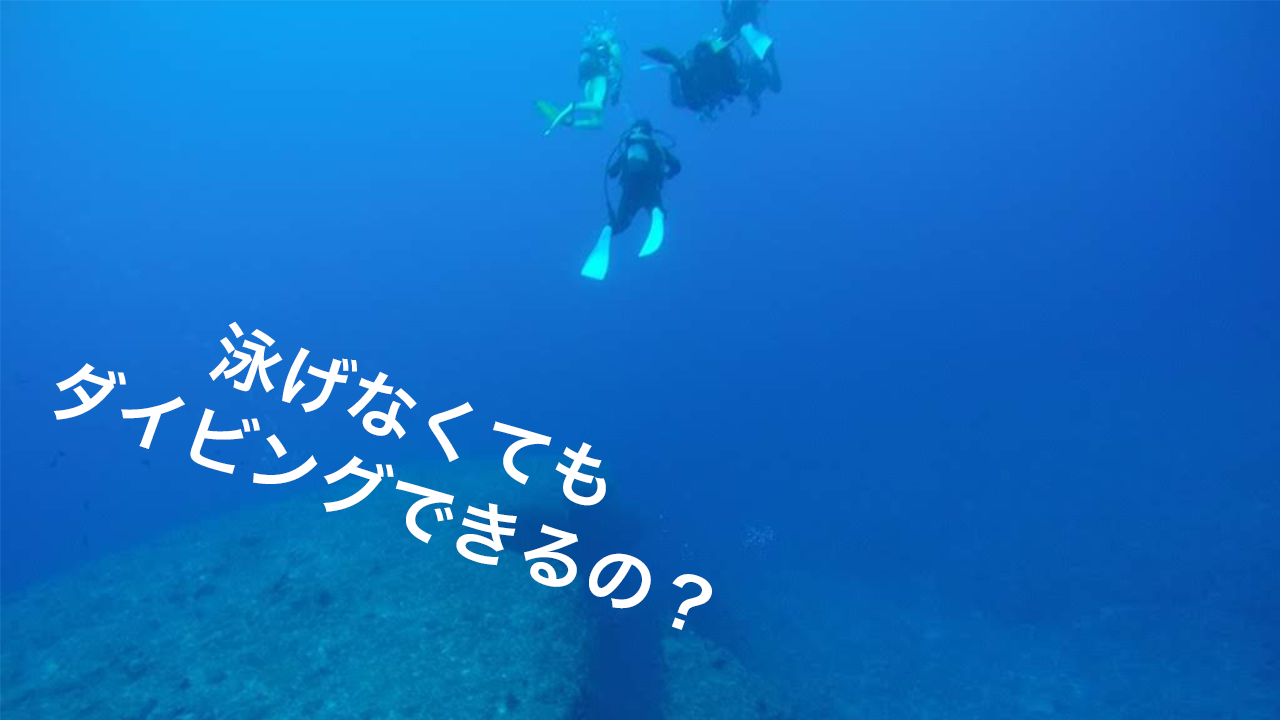
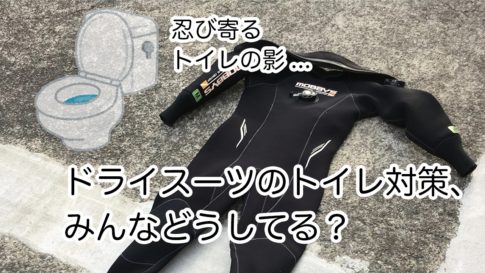
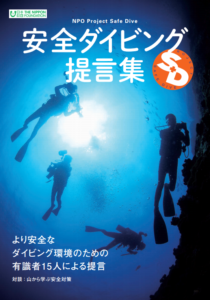
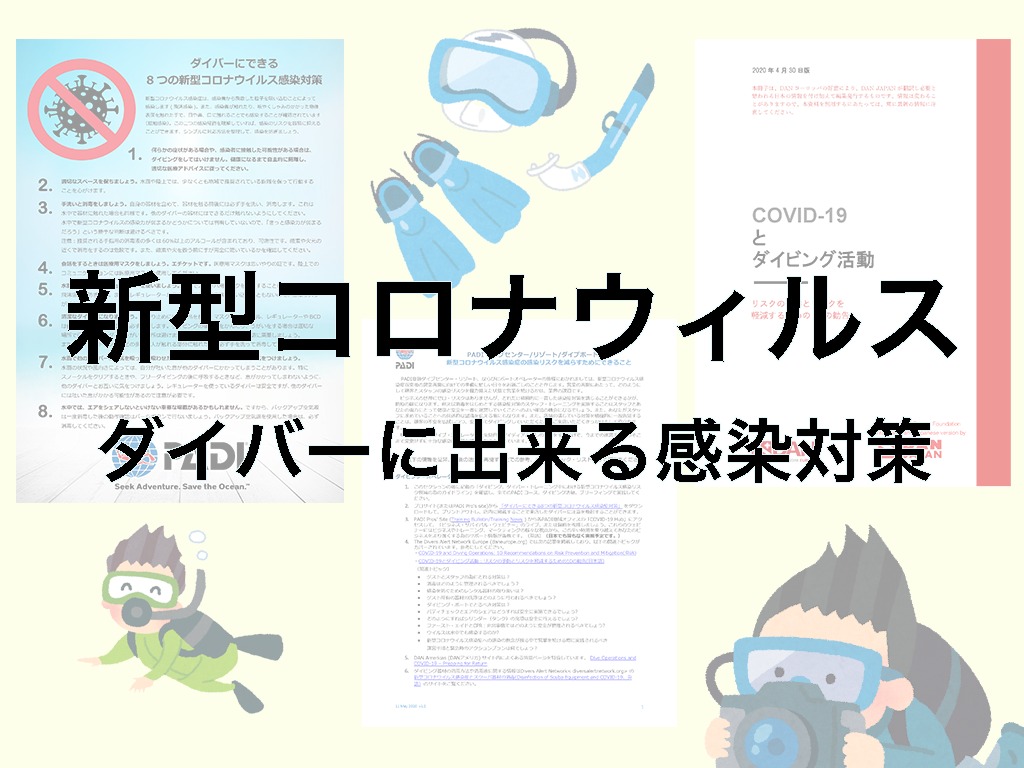








PADI REDでもまずは自分の安全と教えますもんね
自己犠牲してまでの救助はダメです
そうですね、自己犠牲はやはり一番考えてはいけないと思っています・・・
判断が難しい場面もあると思いますが、まずは自分の命が最優先、という基準を揺るがさないで行動できると良いですよね。